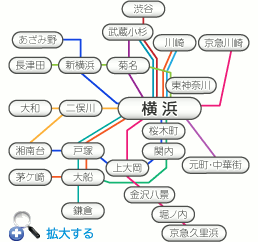盗品等保管罪とは、盗品等を保管する犯罪です。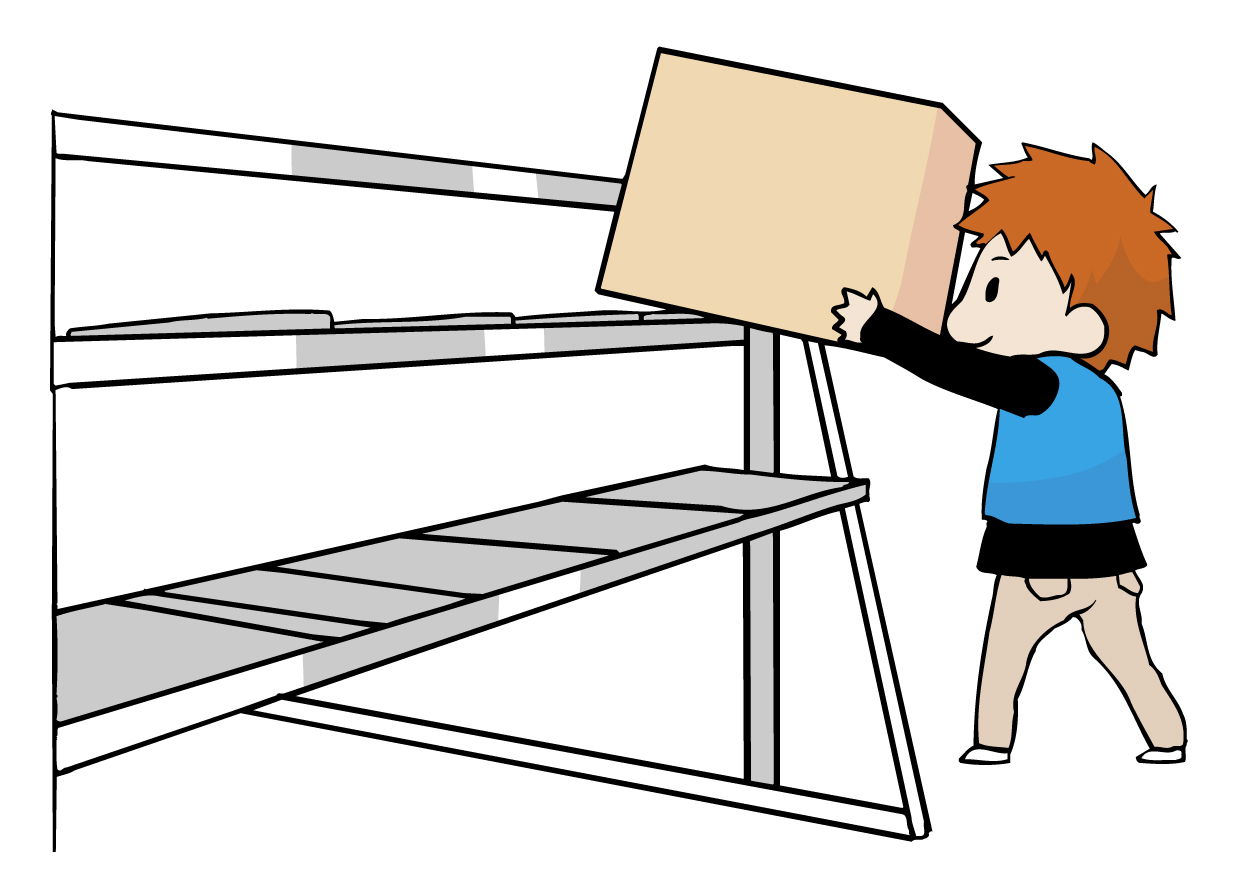
刑法256条2項に規定があります。
盗品等保管罪の刑罰は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金です。
盗品等の保管とは、委託を受けて盗品等を受け取り保管することです。
保管することを約束しただけでは、盗品等保管罪は成立しません。
現実に保管を開始した時点で、盗品等保管罪が成立します。
保管することについて、その対価を受け取る場合でも受け取らない場合でも盗品等保管罪は成立します。
また、単なる保管だけを請け負うというだけでなく、有償や無償で借りる場合や、質物として受け取る場合などでも、保管行為があれば、盗品等保管罪が成立します。
それから、委託を受ける相手は、盗品等の犯人だけでなく、例えば犯人から委託を受けて盗品等を運搬した者(盗品等運搬罪を犯した者)の場合でも盗品等保管罪になり得ます。
盗品等保管罪は、第三者が盗品等を保管することによって、被害者が盗品等を追求・回復することが困難になること等から、犯罪として処罰されることになっています。
盗品等保管罪は、窃盗犯本人が盗品を保管したとしても成立しません。
犯人以外の第三者が保管した場合に盗品等保管罪が成立します。
盗品等保管罪が成立するには、保管している物が盗品等に該当することを知っていることが必要です。
盗品等は、盗品等無償譲受け罪と同様、窃盗罪だけでなく、強盗罪や横領罪などの犯罪の目的物を含みます。
盗品等であることを最初は知らないで保管を開始し、その後に盗品等であることを知りながら保管を続けた場合に、盗品等保管罪が成立するかどうかについて学説上争いがあります。
この点について、最高裁は、盗品等であることを知った後は盗品等保管罪が成立することを認めました(最高裁決定昭和50年6月12日)。